今週は猛暑日がやってくるとか。
まだ6月も半ばというのに、この陽気。
気候変動の行末が案じられます。
それでもなお、今回の七十二候はぴたりと季節を言い当てました。
6月15日頃までを腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる)と称し、蛍飛び交う頃合い。
本日は6月16日。
本来であれば、本日から次の候に入るべきところ、あえて本日はこちらにて。
つい先日、祖母が他界した。
100歳を超える長寿を保ち、自分で歩き、体操し、旺盛な食欲で母の用意する食事を「美味しい、美味しい」と食べていた。
突如として歩けなくなり、食が極めて細くなったのは、息を引き取るほんんの数日前。
それから2日ほどこんこんと眠った後、とても穏やかに旅立った。
100歳を過ぎた葬儀には、紅白饅頭を配るという。
天寿をまっとうした大往生はおめでたい。
100歳を過ぎた葬儀に巡り合うことは人生に1回あるかないか。
担当してくださった葬儀社の方ですらそうだという。
紅白饅頭の入ったずしりと重い袋を手渡しながら、そう教えてくださった。
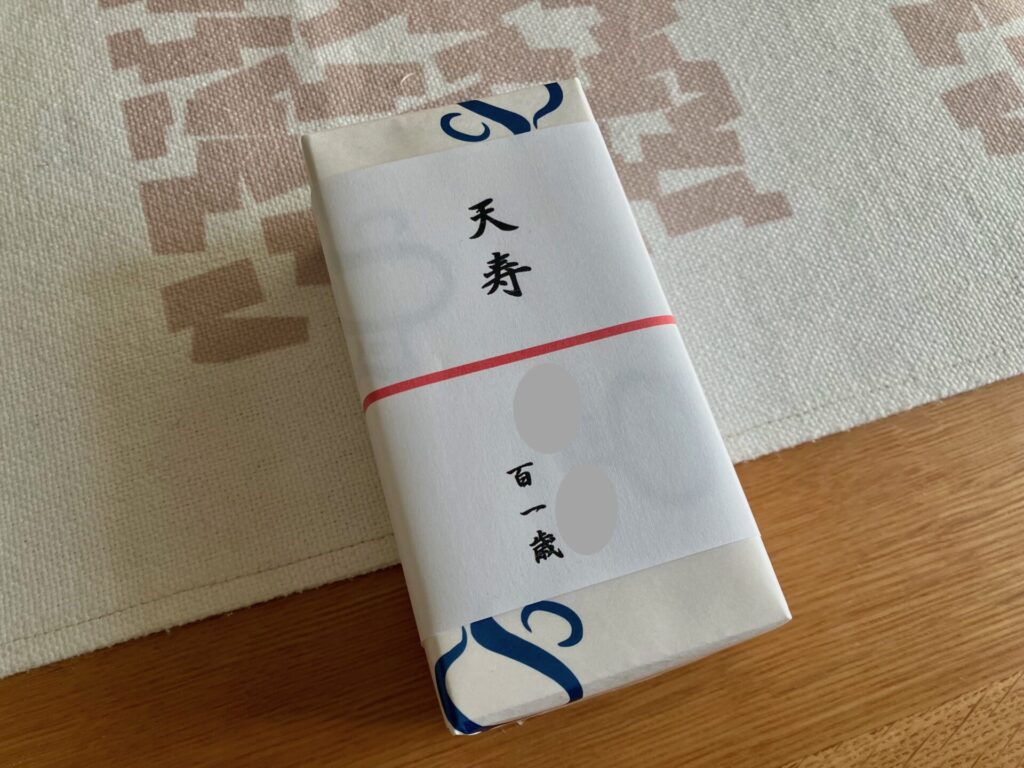
もちろん、祖母がこの世にいなくなったことは寂しいことに違いない。
けれども、「おめでたい」ということにも大いにうなずける。
人がもつ、本来の生命の力をほとんど最大限まで保ち、歩き続けた100年余り。
大正に生まれ、太平洋戦争の戦禍をくぐり、昭和から平成へ、そして令和へと生き抜いた。
そこまで歩み続けることができたことへの賞賛は、心に、そして発する言葉に自然と湧き出てくる。
さて、通夜を終え、会場から鎌倉の山間の実家へと戻った。
と、同行の母が、「あ……」と声を上げた。
見上げれば、鬱蒼とした夜の闇の中、黄緑の色をした光がふわりふわりと浮かんでいる。
一匹の蛍だった。
「おばあちゃんじゃないかしら」
母が言う。
たった一匹、小路を辿るように、それは家の裏へと私たちを導いていく。
祖母の介護で手入れのままならなかった小路には、草が生い茂り、木の枝が行手を阻む。
その中へと分け入ろうとする母の後ろから、暗闇の向こうを伺うと……
もう一匹の蛍が、ふわりと舞った。
「部屋から見えるかも?!」
大急ぎで家へ上がると、山に面した部屋の雨戸を開ける。
と、谷戸の奥の闇の中、蛍が光った。
少なくとも、五、六匹はいただろうか。
谷戸の木立の中、ことさらに濃い闇の中に点滅し、ふわりと舞い上がっては消えていく。
「蛍がいるのよ!」
電話で近隣に暮らす親戚に知らせる母。
早速にやってきた親戚らと、抑え気味の歓声を上げながら蛍鑑賞会となった。
「前はいっぱいいたのに、最近、いなかったよね」
そう、何十年も前には、この界隈にも蛍がたくさん飛んでいた。
夏になると親戚が集まり、庭でバーベキューやスイカ割り、花火に興じた。
気づくと、酒宴に興じていた祖父の姿がない。
やがて、戻ってきた祖父が軽く握った手を開くと、そこに小さな蛍の灯りがあった。
その後、祖父が他界し、水質の汚染もさることながら、家を取り巻く水流が変わったのか、蛍を見ることは稀になった。
そして、今度は父が蛍を探してくれた。
けれども、その頃、軽井沢に暮らしていた私は、残念ながら蛍を見ることはほとんどなかった。
その父も、とうにこの世の人ではない。
蛍の光に、父のことも思い出される。
まだ健在だった頃、父は草を刈るため、蛍の通る小路に面した山の斜面に登ったものだった。
そうして山を手入れした年は、ヤマユリの花が見事に茎を伸ばし、いくつもの大輪の花を咲かせた。
祖母が他界する直前、今年最初のヤマユリの花がひらいた。
それをベッドがから眺めた祖母は、まもなく逝った。
昔、夏の庭での親戚の集いは、一大イベントだった。
最年少のいとこは、今でも目を輝かせてその時の話をする。
そして必ず、今は亡き祖父母や父のことに話は至る。
時は過ぎ、人は去っていく。
生きている私たちは、いつでこの世を去った人々のことを想うことができる。
そしてもし、それを共有できる誰かが周りにいるのであれば、それほどに幸いなことはない。
祖母の書き初めが遺されている。
書に通じ、平安の頃の名筆かと思わせるような筆を多數遺した祖母。
ところが、その最期の書き初めのお題は、思いのほかに庶民的とでも言おうか。
デイケアセンターで用意されたお題から選んだものだというその書には、こうある。
「くよくよしない」。
その一言は、まさに祖母の生き様だったというのが、母や近しい親戚の一致するところである。
自身の不調が苦労について、一言も愚痴ることはなかったという祖母。
多くの苦難を乗り越えて、100年余りを生きた。
長生きの秘訣は「くよくよしない」、かもしれない。

